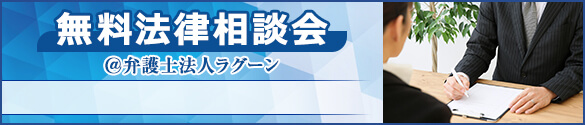臨時号!メルマガ記事 「 新型コロナウィルスと法務について 」
弁護士の内田です。
新型コロナウィルスの感染拡大は未だ終息する気配がなく、個人の私生活・企業の事業活動に深刻な影響をもたらすに至っています。
そこで、臨時便として、今回は「新型コロナウィルスと法務」と題して、現在の状況において企業を採るべき対策についてお話しようと思います。
1 対従業員との関係について
(1)新型コロナウィルスへの感染が疑われる場合
従業員から体調が悪いとの報告があった場合、ほとんどの場合、会社は出勤を免除していると思いますが、では、体調不良を理由として欠勤させた場合、その従業員の賃金は どのように取り扱ったらよいのでしょうか。
まず、基本的なこととして、雇用契約においては、労働者は債務の本旨にしたがった労務の提供をする義務があり、会社はこれに対して賃金を支払う義務を負います。これを裏 返していうと、債務の本旨にしたがった労務の提供が客観的にみて不可能といえるような場合には、出勤を拒絶できますし、また賃金の支払義務も生じません。
仮に、新型コロナウィルスの感染がPCR検査で陽性の結果が出ているなどにより明らかな場合には、出勤により会社の他の従業員への感染拡大はほとんど確実ですから、社会通念上「債務の本旨にしたがった労務の提供」は不可能と判断してよいと考えられます。
では、熱が37.5°以上あるが強い倦怠感や呼吸困難などの症状はないという場合は、どのように判断したらよいでしょうか。
まず、上記の熱に加えて「武漢への滞在歴がある。」「PCR検査で陽性とされた者と接触したことがある。」というような事実も認められる場合には、新型コロナウィルスに感染している高度の蓋然性があるといえますし、そうである以上、社会通念上債務の本旨にしたがった労務の提供は不可能といえますから、出勤を拒否し、賃金を支払わないことも法的に許容されるものと考えられます。
実際に判断に困るのは、熱は37.5°以上あるが、倦怠感・呼吸困難などの症状はなく、武漢への滞在歴や感染者との接触も確認されていないという場合でしょう。
このような場合、専門家によっても意見は分かれるかと思われますが、私見としては、新型コロナウィルスへの感染の高度の蓋然性がない以上、社会通念上債務の本旨にしたがった労務の提供が不可能とまではいえず、出勤を拒否した上で賃金不払いとすることはできないと考えます。
このような場合、「業務命令」として自宅待機を命じ、通常どおりの賃金を支払うという措置を採ることになります。勿論、任意に有給を使用してもらえるのであれば、有給として処理することも可能です。
なお、ここまで述べたことはあくまで「自宅では仕事ができない」ことが前提であり、プログラミングなどの自宅でも遂行可能な仕事については、積極的に自宅にて行ってもらうようにした方がよいでしょう。
(2)お客様が来ないために操業できない場合
従業員に新型コロナウィルスへの感染がなく、またその疑いがない場合であっても、新型コロナウィルスに対する警戒からお客様が激減し、「お店を開けることができない」「工場を稼働させることができない」という状態になり従業員の出勤を拒否した場合、従業員の賃金はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
これについては、労働基準法に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には、会社は従業員に対して平均賃金(簡単にいうと直近過去3カ月の総賃金を直近過去3カ月の日数で割った金額)の100分の60を支払わなければならないという規定があります(同法第26条)。
この「使用者の責に帰すべき事由」という文言だけをみると、「新型コロナウィルスの蔓延は会社のせいではないのだから休業補償を支払う義務は生じないのではないか。」と思われる方もいらっしゃるでしょう。ここについても、専門家で意見の分かれるところだと思われます。
ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、不可抗力を除き広く会社側の事情による場合を指すものと解釈されており、たとえば、機械の検査、原料の不足、監督官庁の勧告による操業停止、流通機構の不円滑による資材入手難なども「使用者の責に帰すべき事由」に当たるとされています。
この度の新型コロナウィルスによる一時閉店は「監督官庁の勧告による操業停止」に準じて考えることもできますし、天変事変などの不可抗力によるものとも考えることもできなくはありません。
会社の業種、サプライチェーンの状況、業務の内容及び方法などの個別具体的な状況に応じて、いずれかの立場に立って賃金を取扱うことにならざるを得ないでしょう。
2 対取引先との関係について
従業員に新型コロナウィルス感染者が出て事業所を一時閉鎖しなければならなくなった場合など、取引先に供給しなければならない商品を供給できなかった場合、取引先に対して債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償義務を負うことになるでしょうか。
この点、2020年4月1日から施行の新民法第415条第1項但書において、「社会通念に照らして債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは」損害賠償義務を負わないとされており、現行法においても、解釈上、同じように考えられています。
そうすると、原則としては、上記のような場合には債務不履行に基づく損害賠償責任を負わないといえるでしょう。但し、厳密には、新型コロナウィルスの影響を受けながら他に合理的な手段を講じれば商品の供給は可能であったというような場合には、「社会通念に照らして債務者の責めに帰することのできない事由によるもの」とはいえないということになりますので、慎重の検討が必要です。
3 廃業を選択せざるを得ない場合
政府も今回の新型コロナウィルス感染拡大を受けて、企業に対する様々な助成・援助を行っていますが、体力の低い中小企業においては廃業を選択せざるを得ないケースもあるでしょう。現に、競争の激しい都市圏では「コロナ倒産」も発生してきているようです。
債務超過で廃業を選択する場合、法律的には「破産」を選択することになりますが、ここでは破産を選択する上で重要なことを1つだけお話します。
それは、「破産も無料(タダ)ではない。」ということです。
破産にかかる費用は、弁護士に依頼するにかかる弁護士費用の他に、裁判所に納める「予納金」というものがあります。
弁護士費用・予納金は破産する企業の規模等により異なり、基本的には大規模になればなるほど弁護士費用・予納金は高額化します。
私が主たる事業地としている下関市においていうと、かなり小規模の会社であっても250万円程度はかかります。実際に破産を検討されている経営者様は、事前に破産に詳しい弁護士に相談して、どの程度の費用が必要となるか確認しておいた方がよいでしょう。
経営者様は、破産するか事業を継続するかの分岐点を定めるにあたっては、上記の弁護士費用・予納金を考慮に入れなければなりません。
通常、企業活動においては売上の発生に伴いキャッシュインがあり、そのキャッシュで仕入先等に支払いを行いキャッシュアウトします。破産する場合には、このキャッシュインがあった段階でそのキャッシュをもって弁護士に破産を依頼するわけですが、そのキャッシュを支払いに回した後に売上が無くなってしまった場合には、弁護士費用・予納金すら用意することができず、破産すらできなくなってしまいます。
いずれにしても、法人の破産には綿密な計画と迅速さが求められますので、「もしかしたら破産を選択することになるかもしれない。」と思うところがある場合には、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。